こんにちは、ウラセツログ編集部です。
WordPressにおける「カテゴリー」は、単なる記事の分類タグ以上の意味を持ちます。
適切に設計されたカテゴリ構造は、SEO対策だけでなく、ユーザーのサイト内回遊を促し、運用のしやすさにも大きな影響を与えます。
にもかかわらず、多くのサイトで「とりあえずの分類」として設置されたカテゴリが放置されてしまい、
- 記事がカテゴリ間で分散し見つけにくい
- 内容が似ている記事が複数カテゴリに重複してしまう
- ユーザーが目的の記事へたどり着けない
といった問題を生み出しています。
本記事では、ウラセツログ流に「カテゴリー設計の裏側」を構造・SEO・UXの3つの軸で丁寧に紐解き、
サイト全体の骨格として機能するカテゴリ設計の具体的な考え方とステップを解説します。
2. カテゴリー設計でよくあるNG例と解決策
カテゴリー設計は、サイトの構造と読者導線を左右する重要な要素です。
しかし、初期設計や運用の中で、よくある落とし穴に陥ってしまうケースも少なくありません。
このセクションでは、ありがちなNG例と、それに対する具体的な解決策を紹介します。
2.1 抽象的すぎるカテゴリ名
✖ NG例:「雑記」「メモ」「考えたこと」など曖昧なカテゴリ名は、SEOにも読者にも意味が伝わりにくく、記事が埋もれてしまいます。
→ ✔ 解決策:検索ユーザーのニーズに即した、具体的でわかりやすいカテゴリ名にする。
例:「SEOライティング」「WordPress運用」「構造設計」など
2.2 複数カテゴリへの重複登録
✗ NG例:1記事に複数カテゴリを設定すると、導線がぼやけ、SEO評価が分散してしまいます。
→ ✔ 解決策:記事は原則「1カテゴリ」に限定し、必要に応じてタグや内部リンクで補う。
これにより、カテゴリごとの情報のまとまりが明確になります。
2.3 カテゴリ数のバランスが悪い
✖ NG例:カテゴリが多すぎて分散したり、逆にすべて1カテゴリにまとめてしまうと、構造が不明瞭になります。
→ ✔ 解決策:サイト規模やコンテンツ量に合わせて、「3〜7カテゴリ」程度に絞る。
カテゴリごとの役割を明確にし、読者が迷わない構造を意識しましょう。
このように、カテゴリ設計は「数」や「名前」だけでなく、意味と構造の設計が重要です。
3. ウラセツ流|カテゴリー設計の具体ステップ
カテゴリー設計は、感覚ではなく構造的な思考で行うべき領域です。
ウラセツログでは、サイトの目的や読者像から逆算し、意味のあるカテゴリ構造を設計することを重視しています。
このセクションでは、カテゴリ設計の具体ステップを3つに分けて解説します。
3.1 サイトの目的・読者像から逆算する
カテゴリ設計は、まずゴールから逆算して考えることが重要です。
「誰に、何を届けたいか?」という視点から、必要な情報体系を設計します。
- 想定読者(ペルソナ)は誰か?
- 彼らが解決したい課題は何か?
- どのような情報のまとまりが必要か?
例:ブログ設計支援サイトの場合
カテゴリ例:
- SEO
- 構造設計
- ライティング
- 収益化
このように、読者ニーズとサイト目的に沿ったカテゴリを設計することで、構造に意味が生まれます。
3.2 トピッククラスタで関連記事を紐付ける
カテゴリは、単なる分類ではなくトピッククラスタとして機能させることが重要です。
各カテゴリに「柱記事」と「関連トピック記事」を紐付けることで、構造的な深みが生まれます。
例:「SEO」カテゴリの構造
SEO
├── SEOライティングの裏側を紐解く
├── 内部リンク設計の裏側を紐解く
└── カテゴリー設計の裏側を紐解くこのように、カテゴリ内で意味のある関係性を築くことで、読者の理解も深まり、SEOにも好影響を与えます。
3.3 カテゴリ設計チェックリスト
カテゴリ設計の質を保つために、以下のチェックポイントを活用しましょう:
- ✔ カテゴリ名は検索ユーザーにとって明確か?
- ✔ 記事は1カテゴリに適切に属しているか?
- ✔ 各カテゴリに5記事以上書ける見込みがあるか?
- ✔ カテゴリーページに独自コンテンツ(説明・ナビゲーション)があるか?
このステップを踏むことで、カテゴリは「ただの分類」から「サイトの骨格」へと進化します。
4. SEOと連動したカテゴリ戦略
カテゴリ設計は、サイト構造だけでなくSEO戦略との連携によって、より強力な効果を発揮します。
このセクションでは、URL設計やナビゲーション要素との整合性を通じて、カテゴリ構造をSEOに活かす方法を解説します。
4.1 パーマリンク設計との連携
カテゴリ構造は、URL(パーマリンク)設計にも直接影響を与えます。
例:
/category/seo/seo-writing のように、カテゴリ階層をURLに反映することで、検索エンジンにテーマのまとまりを明確に伝えることができます。
このような設計により:
- 検索エンジンがサイト構造を理解しやすくなる
- URL自体がコンテンツの意味を持つようになる
4.2 サイトマップ・パンくずリストとの整合
カテゴリ構造は、サイトマップやパンくずリストの整備にも密接に関係しています。
これらの要素がカテゴリ設計と整合していることで:
- クロール効率が向上し、検索エンジンに正しく情報が伝わる
- UX(ユーザー体験)が改善され、読者が迷わず目的の情報にたどり着ける
このように、カテゴリ設計はSEOの技術的要素とも連動させることで、構造的な強さと運用のしやすさを両立できます。
5. カテゴリーページを「生きたページ」に育てる
多くのWordPressサイトでは、カテゴリーページが単なる記事一覧に留まりがちです。
しかし、ウラセツログではこのページこそが、設計思想を体現する場であると考えています。
カテゴリーページは、読者にとっての「入口」であり、検索エンジンにとっての「構造の証明」です。
ここを丁寧に設計することで、SEOとUXの両面で大きな効果を生み出すことができます。
カテゴリーページに必要な要素
カテゴリーページを「生きたページ」に育てるためには、以下の要素を意識しましょう:
- カテゴリ全体のテーマや狙いを示す説明文
300〜600字程度で、カテゴリの目的や読者への価値を明示する。 - 人気記事や新着記事のナビゲーション設計
読者が次に読むべき記事を迷わず選べるように配置する。 - 関連タグやシリーズ記事への誘導リンク
カテゴリ内の情報をさらに深掘りできるように、構造的な導線を設ける。
こうした設計により、カテゴリーページ自体がSEO価値を持つコンテンツページとなり、
読者を導く「案内板」として機能するようになります。
まとめ|カテゴリは「設計」で差がつく
カテゴリは「なんとなく作る分類」ではありません。
明確な設計思想に基づいて構築することで、サイト全体の質が大きく変わります。
カテゴリ設計がもたらす主な効果:
- SEO評価の向上
- ユーザー体験の改善
- サイト運用の効率化
WordPressの自由度の高さを活かし、
サイトの骨格となるカテゴリ構造を見直すことが、信頼されるブログへの第一歩です。
▶ さらにサイト構造を強化したい方へ
「内部リンク設計の裏側を紐解く|SEOと読者導線を両立する構造設計の技術」もぜひ合わせてご覧ください。
カテゴリ設計の具体的な相談や、自サイトへの適用方法について気になることがあれば、
こちらからお気軽にお問い合わせください。
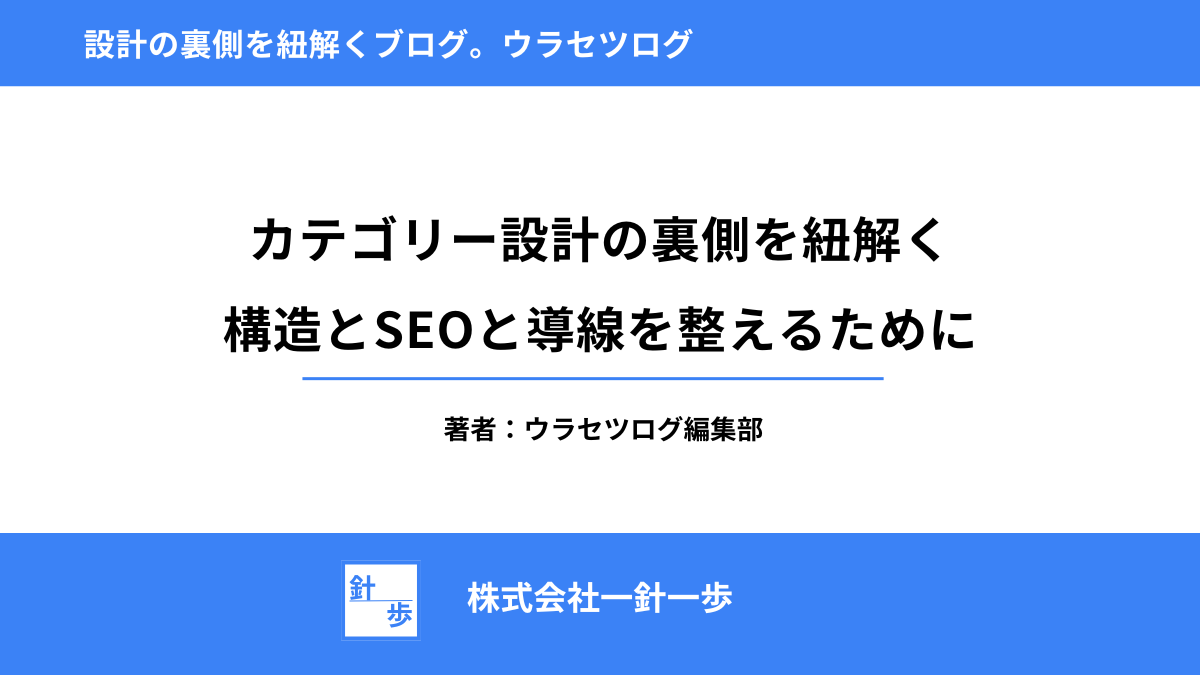

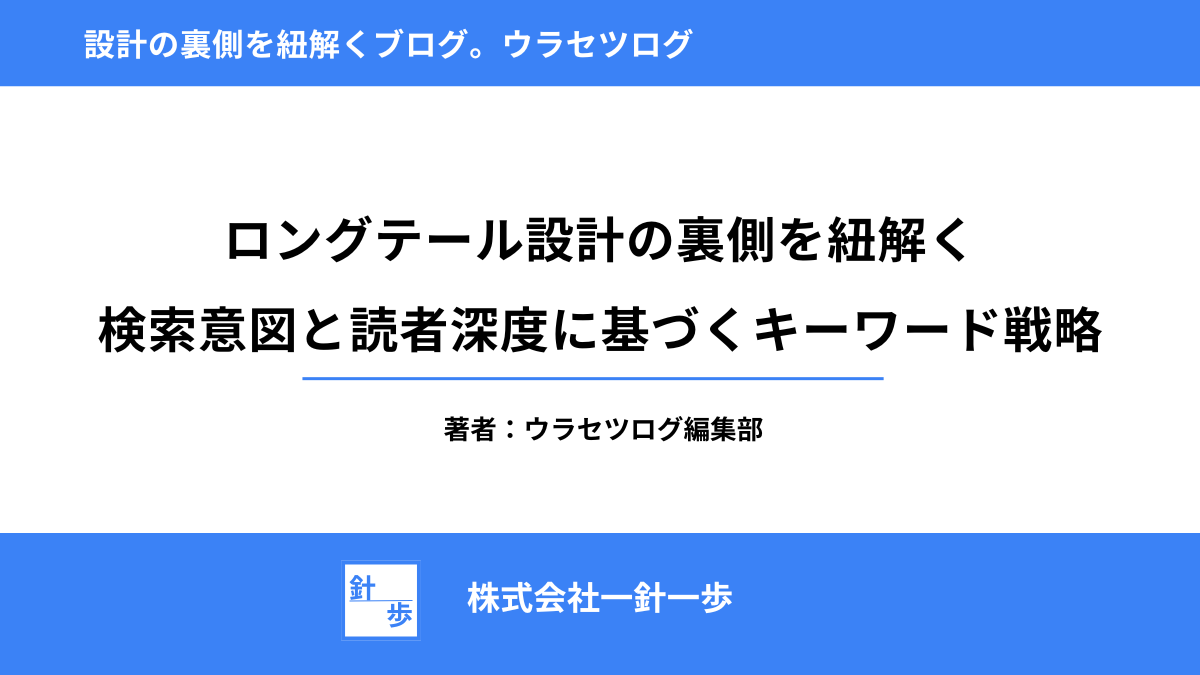 ロングテール設計の裏側を紐解く|検索意図と読者深度に基づくキーワード戦略
ロングテール設計の裏側を紐解く|検索意図と読者深度に基づくキーワード戦略 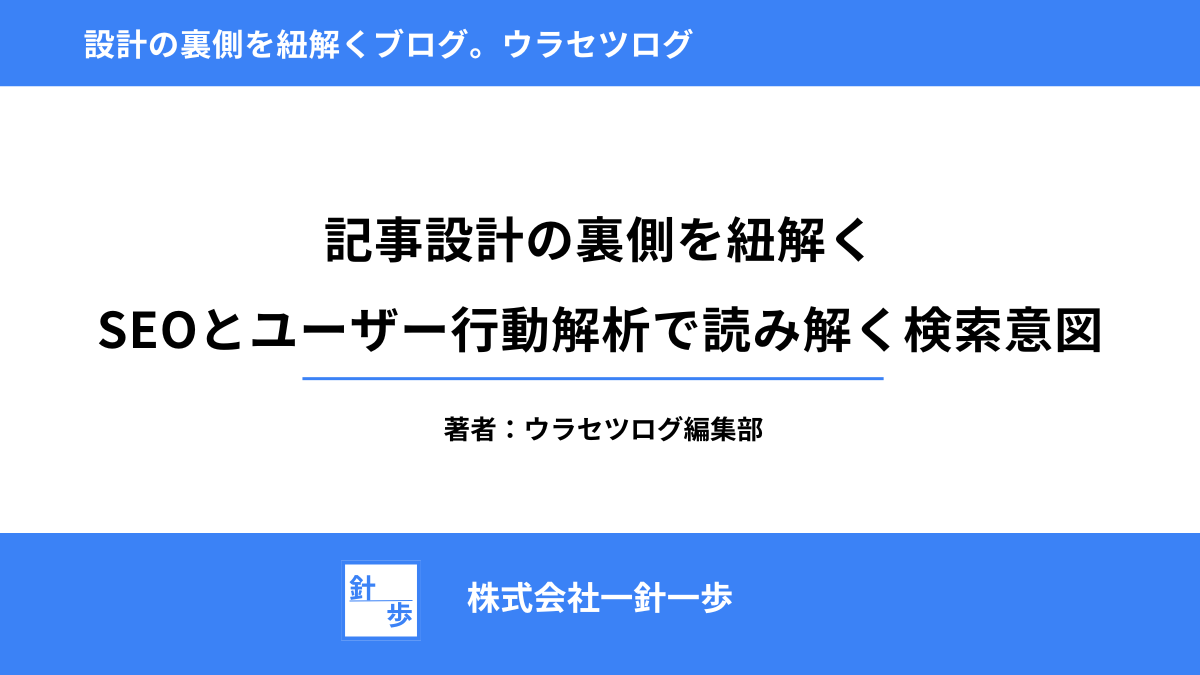 記事設計の裏側を紐解く|SEOとユーザー行動解析で読み解く検索意図
記事設計の裏側を紐解く|SEOとユーザー行動解析で読み解く検索意図 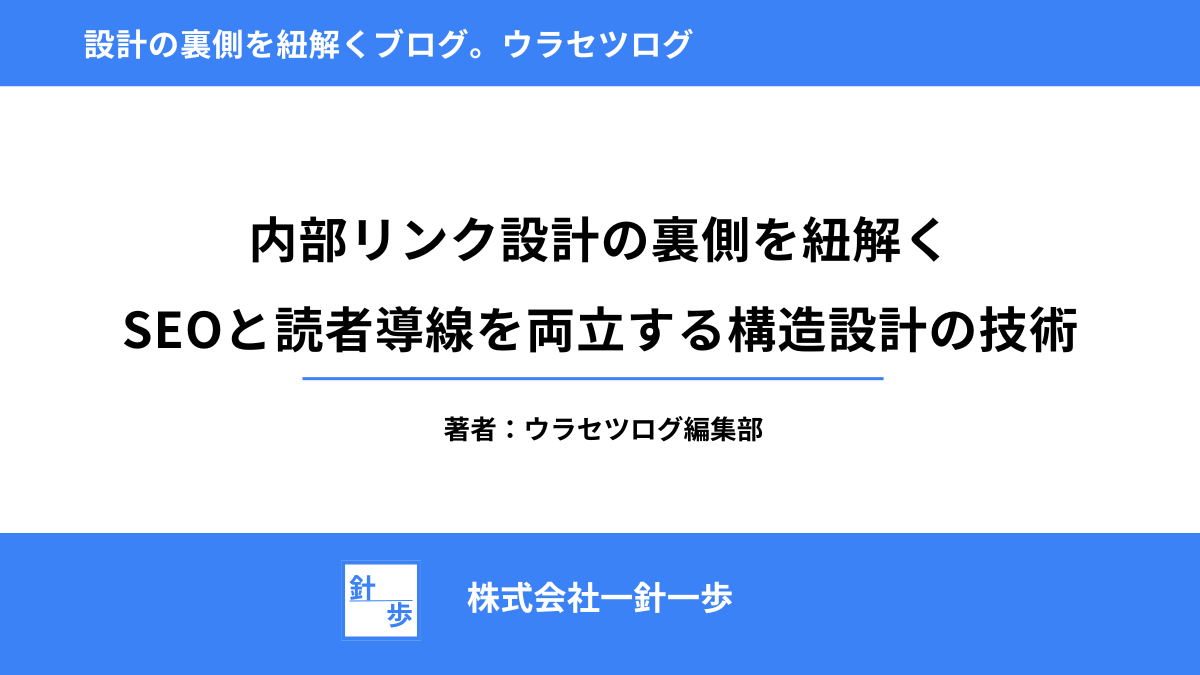 内部リンク設計の裏側を紐解く|SEOと読者導線を両立する構造設計の技術
内部リンク設計の裏側を紐解く|SEOと読者導線を両立する構造設計の技術 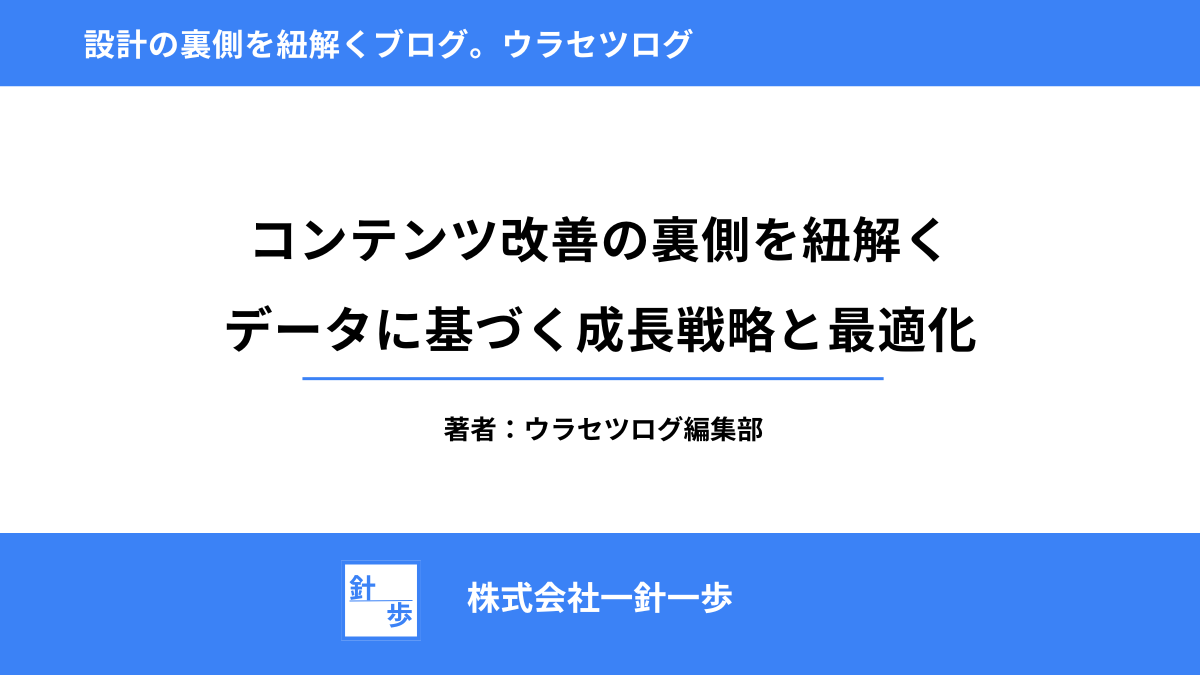 コンテンツ改善の裏側を紐解く|データに基づく成長戦略と最適化
コンテンツ改善の裏側を紐解く|データに基づく成長戦略と最適化