WordPressでサイトを設計する際、
「コンテンツごとに投稿タイプを分けたほうが整理しやすい」
そう考えるのは、ごく自然なことです。
カスタム投稿タイプ(CPT)は非常に便利で、特定の情報を独立して管理でき、一覧表示や表示制御にも柔軟に対応できます。
しかし、私たちが実際のプロジェクトを通して感じてきたのは、「構造を増やすことは、運用の負荷にもなる」という現実です。
今回は、カスタム投稿タイプを導入する前に立ち止まりたい「設計の視点」についてお伝えします。
なぜ、すぐ「カスタム投稿を作る」選択をしがちなのか?
Webサイト制作の現場では、以下のような意図でカスタム投稿を導入するケースが多く見られます。
- 管理画面をすっきり分けたい
- 特定の投稿だけレイアウトや構成を変えたい
- 「投稿」と「ニュース」を別に扱いたい
こうした設計は一見“整理されているように見える”ため、初期段階では好まれがちです。
しかし、実際に運用が始まってみると、以下のような課題が生まれることも少なくありません。
運用が始まって見えてくる「分けすぎ設計」のリスク
- 作ったカスタム投稿タイプに記事がほとんど増えない
- 管理画面が増えすぎて、どこに何があるか分かりにくくなる
- 更新が属人的になりやすく、運用フローが複雑化する
- 検索・一覧ページ設計が冗長になる(デザイン・実装コストがかさむ)
つまり、「分かりやすくするために分けた構造」が、かえって“扱いにくさ”を生んでしまうことがあるのです。
投稿+カテゴリー+タグで足りるケースも多い
たとえば「お知らせ」や「事例紹介」など、内容がシンプルな情報群については、以下のように整理することで十分対応可能なケースが多くあります。
- 投稿(Post)を使い、
- カテゴリーで分類(例:「お知らせ」「実績」など)し、
- タグで細分化(例:「リニューアル」「障害報告」など)する
このように既存の投稿機能を活用すれば、無理に投稿タイプを増やさなくても、情報の整理と表示の最適化が可能です。
増やす設計より、増やさない判断にこそ技術が要る
カスタム投稿タイプは、便利な一方で、「増やせば便利になる」わけではありません。
ときにはあえて「作らない」ことが、運用に強い構造につながることもあるのです。
- カテゴリーで十分か?
- 固定ページで代用できないか?
- タグで補完できるか?
このような視点で見直すことは、ユーザーの操作性、管理者の業務負荷、開発後の保守性すべてにおいて大きな意味を持ちます。
「まず作る」ではなく、「本当に必要か」から始める
設計の起点は、「作りたい機能」ではなく、「必要かどうかの判断」です。
便利そうに見える構造でも、それが実際に使われなければ意味がありません。
長く使えるWebサイトを支えるのは、華やかさよりも、堅実な設計です。
だからこそ、最初に問いかけたいのです。
「そのカスタム投稿、本当に必要ですか?」

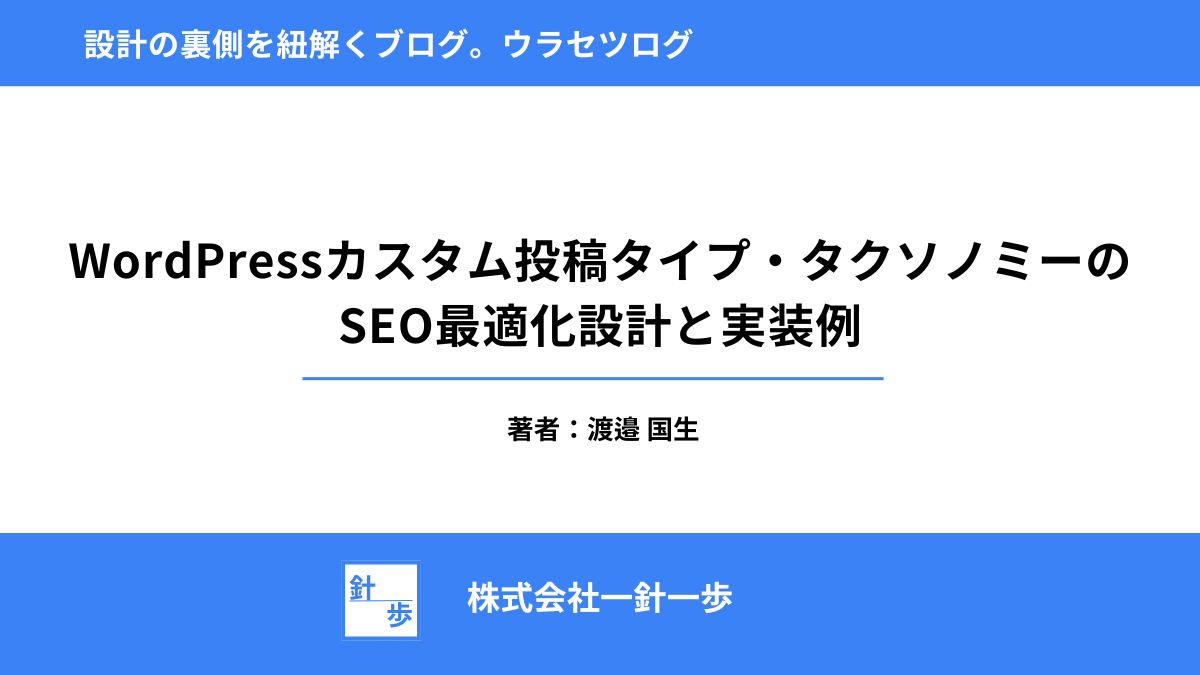 WordPressカスタム投稿タイプ・タクソノミーのSEO最適化設計と実装例
WordPressカスタム投稿タイプ・タクソノミーのSEO最適化設計と実装例